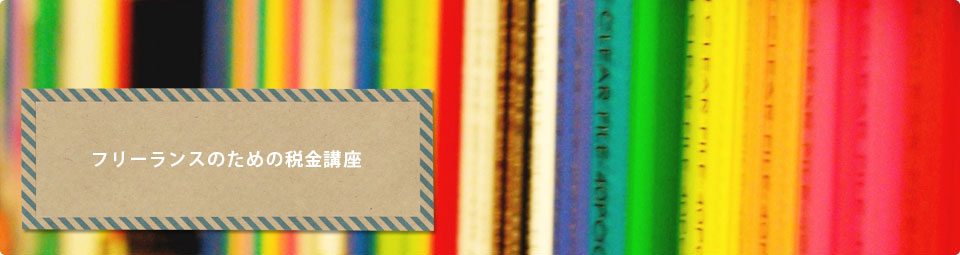osusume
フリーランスならではの節税対策

フリーランスの節税方法を紹介します。まず、申告できそうな経費をピックアップします。仕事でインターネットを使うならパソコン、出張や取材をするなら交通費や宿代など経費にできそうなものは細かくても掘り下げていきます。次に、確定申告の際は青色申告で行ないます。青色申告は特別控除があったり損失の繰越が可能であるなど、メリットがあります。また、配偶者を専従者として給与を支払うことでその人件費も経費として申告が可能になります。そのほかにも、控除を増やすかつ将来に備えるという意味で、保険料の前納や未納分の追納なども有効です。また、国民年金基金や廃業の際の保障として小規模企業共済への加入も節税につながります。
フリーランスの医療費控除はどんなときに使える?

確定申告の際、所得から差し引くことができる控除の中で「医療費控除」というものがあります。フリーランスや個人事業主の場合、申告の際には申告書Bを使用します。医療費控除とは、年間で10万円以上の自己負担の医療費があった場合に適用できます。また、医療費を申告する権限は、その医療費を支払った家族にありますので、一家で合わせて10万円以上かかった場合も申告ができます。レーシック手術やインプラント、歯列矯正の手術費用や治療費についても、医療目的のものであると認められれば医療費控除の対象となります。ただし、美容目的などの場合には適用されません。
面倒なクレカの複式簿記の仕分け

フリーランスが確定申告をする際に、「青色申告」の特別控除枠を守ろうと複式簿記を厳密に発生主義で記帳するならば、クレジットカード取引では面倒なことになります。現金払いであれば問題ないのですが、クレジットカードは取引日と支払日が異なっていて多くは月を跨ぐため、1回の取引につき2回の記帳が必要になります。しかしこれを支払日で統一して記帳する方法も認められており、年度末だけは年度を跨ぐために未払い金で処理する必要がありますが、大部分は1回の取引につき1回の記帳で済むのです。もっとも事業用も個人用も同じクレジットカードの場合には、それでも処理が面倒であり、手間か節税効果かの選択になります。
読んで損はない!税金に関する記事一覧
フリーランスは大切な資金を必要な部分に投下し、売上げを上げつつ、いかに利益を多くするかを必死で考えている人が多いと思います。ところが節税の知識がないと、そのようにせっかく稼いだ利益から不必要に多額の税金を納めることになってしまいます。せっかく利益が出たのに税金のために借金をするというのも冗談ではなく、ありえる話です。そんなことにならないように、正しい節税知識をつけて、賢く節税しましょう。フリーランスの節税キーワードは、経費と控除です。計上できる経費は全てもれなく計上し、該当する控除はすべて申告することが節税の基本です。
フリーランスの節税対策としておさえておきたいのが「医療費控除」に関する知識です。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、控除対象となるという制度です。具体的には、10万円以上の医療費の、10万円を超えた部分が対象となります。つまり、年間の医療費合計が12万円であれば2万円が控除対象となります。病院や薬代など、医療関係の領収書もきちんと保管しておきましょう。レーシックやインプラントなど、意外なものが医療費控除の対象となる場合もあります。医療費控除について詳しく解説します。
フリーランスの場合、事業にかかった経費の支払いをクレジットカードで決済することも多いと思います。クレジットカードの取引を複式簿記で帳簿付けする場合の処理に悩んでいませんか?クレジットカードは、取引日(カードをきった日)と現金支出日(引き落とし日)が異なるので、どちらの日付で記録したらいいのか悩む人が多いようです。複式簿記の原則は発生主義ですので、厳密にいえば、未払勘定で取引日と決済日の両方をそれぞれ記録しなければなりません。そのため、帳簿付けは現金払いよりも面倒になります。具体的な処理方法などを解説します。